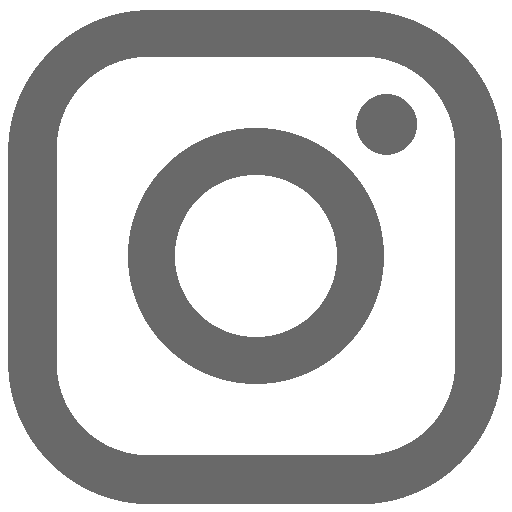2017/04/26
Food
「お寿司」とワインのマリアージュを楽しもう

世界文化遺産にも登録された和食。なかでも「寿司」は、外国の方からも注目度の高いキング・オブ・和食といっても過言ではないでしょう。
お寿司のお供といえば、お茶や日本酒をイメージしがちですが、実はワインとも相性抜群。お寿司の歴史をたどりつつ、現代の名職人さんにワインとのマリアージュのコツを教えていただきます。
江戸前寿司は新しい? 寿司の歴史
スシ、鮓、鮨、寿司——「おすし」とひと口にいっても、時代によってその表情はさまざま。そもそものはじまりから、ひもといてみましょう。
そもそものはじまりは?
スシのはじまりは馴鮓(なれずし)
お寿司というと江戸前のイメージが強いかもしれませんが、日本の歴史に登場する寿司の中では、江戸前寿司はかなり新しいもの。
元々「スシ」とは、食物を発酵させて酸っぱくしたモノ。「酸っぱい」という意味の「酸し」が語源といわれています。いまでも琵琶湖近辺の名物になっている鮒寿司のように、塩と米で魚を漬け込んで、発酵させたものです。したがって「スシ」の当初は、現在でいえばネタを食べるもので、米は調味料や保存料の役割を果たすものでした。
こうした古代のスシですが、ものによっては何十年も漬け込んでドロドロの塩辛状を食べるケースも。たとえば、紀州熊野の秋刀魚ずし。秋刀魚も米も一緒くたで、見た目はちょっと凄いものですが、味は絶品。こうして古代から中世にかけて徐に、スシ=ネタを酸っぱく発酵させた食品から、スシ=ネタと米を一緒にして食べるモノ…という概念が広まっていきました。これらを大まかに『馴(なれ)ずし』といいます。
「おじゃれずし」「まちゃれずし」「早ずし」
馴ずしは、米を発酵させるわけですから作るのに大変時間がかかります。だから一名『おじゃれずし』。出来るまでに何ヶ月もかかるから、注文すると「ふた月後に取りにおじゃれ」と、いうわけです。中には、「そんなに待てないよ」という人もいたことでしょう。
そこで考え出されたのが「待ちゃれずし」。米と具を仕込んで重石をかけたり、菰をかけて火で炙ったりして発酵を早めたものです。できあがるまでにおよそ一昼夜かかるので、「ひと晩待ちゃれ」で、「待ちゃれずし」。今の押し寿司の先祖のようなかたちだったと考えられます。
しかし、いつの時代にもセッカチはいるもの。スシをつくるにも「おじゃれ」だの「まちゃれ」だのと、あまり悠長なことを言っていられなくなり、米の発酵を待つのではなく、酢を使って魚を締めたり酢飯を拵えて酸味をつけるようになります。このスシは発酵を待つ必要がないのですぐにできます。ゆえにこれを「馴ずし」に対して「早ずし」といいました。
「酸っぱいというのがスシの語源なら、どうして最初から酢をつかわなかったの?」と思うかもしれません。しかしそれは、現代人の発想です。確かに奈良平安の昔から酢はありましたが、炊いたり、蒸したりするだけで美味しく食べられるお米を、贅沢にも酒に拵えて、あまつさえ酢にしてしまうのですから、穀物酢は大変貴重な調味料だったのです。
早ずしが生れた時期には諸説ありますが、ちょうど豊臣秀吉が天下を統一した頃と思えば、遠くありません。平和な時代をむかえ、農業生産力が上がり、庶民でも酢を使えるようになったでしょう。
いずれにしても、早ずし誕生の舞台は関西と考えられます。今でも大阪には、押寿司(箱寿司)の形体が遺っています。これは、酢を使うようになってからも、箱や樽に漬け込んで発酵させていた時代の名残りでしょう。
江戸のすし
酢を使った押寿司や箱寿司は江戸にも伝わり、徳川時代の中期を過ぎる頃までは、それが江戸のすしの主流でした。そうしたすしのひとつが、今も遺っている〈笹巻毛抜鮨〉。酢で味を付けた早ずしですが、笹で巻いたり箱に詰めたりすることから、古い押寿司や箱寿司の系譜にも連なっているものと察せられます。江戸時代、この鮨は大奥をはじめとする御殿女中衆に大層親しまれたそうです。御殿女中といっても若い女の子には違いがありませんから人並みにお腹は減ります。夜中にお腹が空くと、水餅やら、沢庵やら、海苔やらこっそり虫養いをしていたといいます。お屋敷で火事を起こしたら大変な罪に問われてしまうので、火を使わずに、自分たちのお部屋で食べられるものばかり。そんな状況で笹巻鮨があったら、どれほどのご馳走だったことでしょう。強く効かせた酢と笹の滅菌効果で日持ちがする笹巻鮨は、お宿下がりをしたお女中が再びお屋敷に帰る際の、何よりも喜ばれる御土産だったそうです。
さて、江戸前の握りずしの登場はというと、江戸時代も後期にさしかかる文化文政の頃(1804~1829)。隅田川東岸の安宅河岸にできた〈松ずし〉が江戸前握りの元祖らしいと『嬉遊笑覧』や『守貞漫稿』にあります。このすしの特徴は、冷蔵庫も無い時代に新鮮なネタを使うことと、酢飯を握りにすること。これまでの押寿司は、型で酢飯を固めていたわけですから、口のなかでサラリとほとびる米の食感には、かなりの洗練が感じられたことでしょう。とはいえこのすしは大変な高級品で、肥前平戸の大名だった松浦静山でさえ、「松鮨は旨いと評判だが値段が高く、五寸の器の二重盛りが三両もする」と驚くほど。到底庶民の口にたやすく入るものではありませんでした。
転機が訪れたのは天保三(1832)年のこと。この年、どういうわけか江戸前の海に鮪の大群が侵入してきたのです。曲亭馬琴の日記によれば、三尺の鮪が二百文だったというから大変な安値で売買されました。そのうえ、折も折、ちょうどこの頃、銚子や野田で醤油が造られはじめ、江戸っ子にとって抜きさしならない調味料になっていました。安くて、旨くて、新鮮で、そして目新しいネタがある。高級な握り鮨に憧れていた江戸っ子は、鮪を醤油でヅケにし、握り鮨を作ったのです。
ここから、江戸前寿司のバリーエーションが一気に広がり、今日の私たちのイメージに直結していきます。鮪のヅケ、小肌、穴子、海老、烏賊などなど、江戸前寿司の特徴は、漬ける、〆る、煮る、蒸す、茹でる、湯引くなどと、いずれも「ひと仕事していること」なのです。
プロが指南する、お寿司とワインのマリアージュ

実は、この「ひと仕事」が、ワインと大変相性が良いのです。その素晴らしい伝統の技を引き継いでおられるおひとりが、銀座〈鮨からく〉のご主人戸川基成さん。
〈鮨からく〉では、一見お刺身に見えるものでも、ただのお刺身ではありません。
たとえば鯛の刺身は、三枚におろした鯛の味に塩を振り、湯引きするという手間がかけられています。こうすることで刺身から余計な水分を抜き、同時に生臭さを処理しているのです。
戸川さんによれば、「ご家庭で応用する際は、なるべく刺身をサクで買い、サクごと塩をして10〜15分ほどおき、水洗いをして水気をとればよい」とのこと。ここに、スダチなどの柑橘をしぼれば、爽やかな酸をもつワインとは抜群のマリアージュになります。
南蛮漬のような酢を使うお料理には、酢の代わりにワインを使う手法も。南蛮酢を作る際、酢を半量にして、代わりに爽やかな白ワインを入れます。
マリアージュの基本は「同調」と「補完」。したがって、料理に使う調味料にこれから飲むワインを少し入れると、料理とワインは同調し、素晴らしいハーモニーを奏でるのです。また、通常は仕上げにレモンなどの柑橘類を絞る魚の塩焼きに、代わりに酸味の強いワインを合わせることは補完のマリアージュ。こうした工夫で、ワインは和食に見事に溶け込みます。
どのようなワインを合わせたらよいでしょうか?とお聞きすると、
「どんなワインでも料理のひと工夫でお寿司に合わせることはできますが、ともかくも合わせやすいのは旨味やミネラルが豊富で、酸味の綺麗な白ワイン。例として挙げるなら、フランスのアルザス知地方のワインなどですね。たとえば、1626年創業のトリンバックさんの白ワイン。凝縮感があり、トロリとした果実の旨味が感じられるリースリング・レゼルヴなどは絶品のマリアージュです。」
と、戸川さん。

「同じトリンバックでも、フラッグシップのクロ・サンテューヌのセカンド的なワイン、フレデリック・エミールのような、ドライで端麗、そして熟成感のある味わいのワインには、火を通し、風味を添えて味わいを深めた料理が合います。鯛をソテーしてバジルのソースをまとわせ、菜の花を添えたりすると、しっくりと寄り添うのですよ。」
長い歴史を持つ「すし」。その伝統に秘められた技の蓄積が、ワインとの比類ないマリアージュを実現させるのです。
関連記事
白ワインと和食のマリアージュ、ポイントは「食感」と「ミネラル感」!